2010年不動産市場の予測
新設住宅着工戸数の回復は見込めるか
平成2年に170万戸をつけた新設住宅着工戸数もこの年をピークに減少し始め、平成10年から平成18年は110万戸〜120万戸台で推移していたが、平成19年に建築基準法改正施行による建築確認業務の長期化等から、対前年比約20%も減少した。
平成20年も平成19年と同じ100万戸台であったが、平成21年では平成21年1月から11月の累計は72万戸弱で、通年ベースで1967年以来42年ぶりに100万戸を割る見込みである。
各種シンクタンクは、2015年までの5年間における平均住宅着工戸数を90万戸前後と予測している。
人口、世帯数の減少や、世帯の高齢化、空家の増加等が主たる要因であるが、筆者は2010年度は90万戸を超え、100万戸前後に達成すると考える。
その根拠として、以下の点を掲げる。
1. 持家取得層の平均年齢38〜39才は団塊ジュニア層の年齢であり、人口層が厚いこと。
2. 新設住宅着工を刺激する経済政策の実施として(a) 住宅のエコポイント制度の創設(1,000億円)や、(b) 住宅金融支援機構による長期固定住宅ローン「フラット35」の金利の引き下げ幅を、現行の0.3%から1.0%に拡大(4,000億円。但し、2010年12月末日までの時限措置)すること。
こうしたエコ住宅、エコリフォームの経済政策は、需要のライフスタイルに合致しており、2010年度の新設住宅着工戸数は100万戸前後にまで拡大すると予測する。
但し、住宅供給側、即ちディベロッパー側が「エコ」を看板として安易にコストアップを計ると、恐らく失敗に落ちいる。
需要の取得環境は依然厳しく、この中でのマイホーム取得は価格追求のみならず、ライフステージにあった住宅の住み方を提案できるものにと選択のポイントは厳格化しており、減築、減床をも視野に入れた商品開発が求められる時代となっているからである。
大阪市商業地の地価
平成19年のアメリカ発サブプライム問題、平成20年9月のアメリカ大手金融機関の破綻により始まった世界経済悪化の影響を受け、平成20年4-6月期以降はマイナス成長に陥った。
しかし、平成21年4-6月期は前期比+2.7%とプラスに転じ、平成21年7-9月期の実質GDPでは、成長率が前期比+1.3%と前期(平成21年4-6月期)を更に上回っており景気回復への期待感が生じている。
これは、平成21年に入り中国を始めとするアジア経済が持ち直していることと関係している。
内閣府の月例経済報告(平成21年12月)においては「景気は、持ち直してきているが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある。」とされ、平成21年10月から11月、12月はほぼ同じ表現であった。
先行きについては、当面、厳しい雇用情勢が続くとみられるものの、海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が続くことが期待される。
一方、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、デフレや金融資本市場の変動の影響など、景気を下押しするリスクの存在も指摘されている。
近畿圏においては、平成21年11月現在では鉱工業生産は緩やかに持ち直しているが、設備投資は総じて大幅に減少、雇用は極めて厳しい状況にあるものの悪化のテンポが緩やかになり、個人消費は一部に持ち直しの動きがみられるなど、低迷しているものの一部に持ち直しの動きがみられる。
ところが、大阪市中心商業地の動向は、昨年下半期に向けて急速に市況が悪化している。
2〜3年前にJリートやファンドにより投資された新築オフィスが2009年に21棟、約13万坪も竣工したことから、供給過剰に落ちいっている。
それに対し、需要は景気後退によるオフィスの閉鎖、縮小から需要減が続行しているため、需給バランスが急速に悪化している。
このため、新規供給オフィスビルが増加し、平均募集賃料は上昇するが空室率は拡大状況にある。
平均募集賃料は上昇しているが、実際の大阪のオフィス市場では平成21年下半期から入居テナントからの賃料減額交渉も多くなり、ビルオーナーの多くは減額に応じている。
賃料減額に応じないと、入居テナントは契約を解除して明け渡しし、より安い賃料のビルに移転する。
このようにオフィス賃料は下落が続行し、空室率も拡大し続けているのが現状である。
賃料が下落する限り、ビルの収益性の回復は見込めず、更に地価が下げ止まることもない。
従って、2010年も引き続き地価は下落するものと予測した。
住宅地の地価
堺市をモデルにしたGDPの変動を乗じた理論地価は、21年後半から上昇に転じたものの、実勢価格は下落が続行している。
景気指数は上昇しているのに、勤労者収入は減少しているためであって、総務省による家計消費指数(実質)でも「二人以上世帯」「単身世帯」ともに「住居費」の支出は減少傾向にある。
2009年では、衣食の分野でも消費者の「低価格」指向が色濃く現われ、「住」の分野も例外でなく2010年も住宅価格の低下、即ち地価の低下は続行するものと予測した。なお、堺市においてはエリア毎に地価の動きに差が出ており、「北区」「中区」は地価下落率は小さいが、「南区」「美原区」は地価下落率が大きい。
こうした二極化の中でその人口構成を分析してみると、大阪市営地下鉄御堂筋線を擁する「堺市北区」と、住宅供給の活発な「深井」駅勢圏の「堺市中区」は「0才〜14才」の児童の割合が高く、「65才以上」の高齢者の割合が低く、平均年齢も42才台である。
それに対し、堺市の中心商業エリアを擁する「堺市堺区」と南海高野線沿線で旧集落が多い「堺市東区」は、高齢化率が23〜24%台と堺市の中でも高く、平均年齢も45才台となっている。特に、「堺市堺区」は児童の割合も12%と堺市の中で最も低い。(<表1>参照)
大阪府下各都市では、各市の中心部に人口、世帯数が集中する傾向が顕著であるが、堺市では従来の堺の商業中心エリアのポテンシャルは低くなり、逆に大阪都心部と直結する大阪市営地下鉄御堂筋線の「なかもず」駅とその周辺(JR、南海「三国ヶ丘」、泉北高速「深井」)のポテンシャルが上昇して、若い世代が集中している。
<表1>
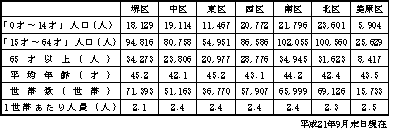
また、区別の人口動態では地価下落の大きい南区は転出が転入を上回り、人口の区外転出が著しい。
美原区では、社会増減の規模自体が小さく、かつ死亡数が出生数を上回り、需要の動きがにぶい。
以上の需要動向が地価の動きを左右しており、その結果として、二極化傾向が顕著となっている。
住宅賃料
「堺市の住宅の地価と理論地価」で前述したとおり、勤労者の実質所得の低下が、住宅賃料を下押ししており、賃料の下落が続行している。
ファンドが供給していた都心部では、高額賃貸物件(家賃15万円超えのファミリータイプ)と、ワンルーム賃料の下落、並びに空室率の拡大が特に顕著である。
ファミリータイプ市場では、家賃帯「8万円〜10万円」の需要が家賃の低い賃貸への移動が目立った。
2009年は、シングル、ファミリータイプとも生活防衛型住み替えの活発な年であった。2009年の新築賃料の下落は、既存の賃貸の賃料の下落に連がるため、2010年も引き続き、賃料は下落するものと予測した。
分譲マンション価格
建築費、地価の下落により2009年は近畿圏、また主要都市の大阪市、神戸市、京都市とも新規マンション価格は下落した。
しかしながら、近畿圏中古マンションの成約件数が2009年の8月以降上昇しているのに対し、マンションの価格下落は契約率の上昇には結びついていない。
需要の低価格指向も理由の一つであるが、マンション販売が諸経費サービス、家具等商品のサービスの値引合戦に落ちいっており、そのマンションで住まうことによる魅力や造り手のコンセプトが伝わってこないことも販売不振の原因であると考える。
2010年上期は、完成在庫の処分が集中すると考えられ、マンション価格は更に低下すると予測した。
