2018年不動産市場の予測
− 住宅地と工業地が調和するまちづくりのために −
住宅地と工業地が調和するまちづくりのために必要と思われることは以下の2点に集約される。
① 行政側の支援として、都市計画による住宅地・工業地の保護
東大阪市では平成25年4月1日に施行された「まちづくり条例」により、宅地建物取引業者に工業地域若しくは準工業地域内の宅地又はこれらの地域内の住宅の売買又は賃借の仲介をするときは、新たに当該宅地又は住宅を取得し、又は借りようとする者に対して、① 工業地域又は準工業地域の趣旨及び概要等、② 公害関係法令に定める規制規準、③ 近隣のモノづくり企業の立地状況、④ 土壌汚染調査に関する情報を有している場合、その情報について説明するよう、努めなければならないとしている。これは、工場事業者と住民側の相互理解を図り、無用なトラブルを避けるためであるが、この条例施行依頼、東大阪市で工場等事業所を探し求める需要が増え、その結果、東大阪市の工業地は地価が上昇し始めている。地価上昇は副次的効果であるが、行政の「ものづくり保護」という姿勢が需要を喚起している成功例である。
② 職住近接立地での高度利用的に多機能を集約した工場アパート等の供給
大阪市中央区南船場四丁目エリアはファッションやカフェが集まる商業ゾーンであるが、かつてはオフィスや事業所が主たる利用の街であった。南方の西心斎橋エリアのアメリカ村を卒業した20歳代が集まるカフェやファッションの店が自然発生的に集まって発展した街であるが、当初はオフィスビルやマンションの上階で衣服をデザイン縫製し、1階の店舗で販売する等、客の反応がダイレクトにものづくりに反映される場でもあった。店舗が集積することにより家賃が上昇し、こうしたファッション工房はなくなっていったが、このように消費者の反応がものづくりに反映される場の確保は必要であり、職住近接立地にものづくりの場を供給することは重要と考えられる。
東京都大田区では文字通り下層階が工場、上層階がマンションの工場アパートを供給しているが、東京都三鷹市の協同組合三鷹ハイテクセンターは、マンションが多く進出する地域にある鉄筋コンクリート造地上4階建の築30年の集合工場である。設立当時20社の入居企業の代表者・従業員は高齢化が進んでいる一方、企業の入退去により、新陳代謝も行われている。ここでは、職住近接立地の中、入居企業の共同受注・共同開発も図られており、24時間操業が可能である。この他、地域社会とコミュニケーションを図るため、環境保全活動、環境防災活動を地域と共に参画し、また地元小学校に対して、教育研修の場として施設を公開している。このような場を多く創出するためにも地元住民と企業が意思疎通を図る場が必要と思われる。
大阪市商業地の地価
大阪ビジネスゾーンのオフィス賃貸市場は、三鬼商事「オフィスマーケット情報」によると、2017年11月時点の平均空室率3.74%、平均賃料11,229円/坪で、空室率が低下し、賃料も上昇と好調である。
理由としては、新規のオフィス供給が少ないという点が挙げられるが、好況感から企業の設備投資意欲が高まっていることも背景にある。
特にオフィス需要は梅田ゾーンに一極集中しており、大阪ビジネスゾーンの平均入居率、平均賃料を押し上げている。
下<表1>は、梅田ゾーンの2013年10月から2017年10月間の延床面積、貸室面積、平均賃料、空室率等をまとめたものであり、<図1>は平均賃料と空室率をグラフ化したものである。
これによると、梅田ゾーンの平均賃料は2014年10月は対前年で下落したものの、その後は上昇しており、2017年10月では、14,487円/坪まで上昇している。更に、空室率は2013年の9.66%から2017年は2.36%まで下落し、梅田ゾーンのオフィス市場に需要が集中し、需給バランスの崩れから賃料が上昇している。
他ゾーンも空室率は低下傾向にあるが、坪1万円以上の平均家賃のビジネスゾーンの中で最も平均賃料が上昇しているのは梅田ゾーンのみである。
<表1>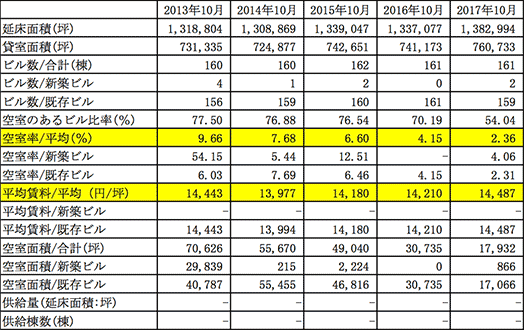
(出典:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ梅田地区より)
<図1>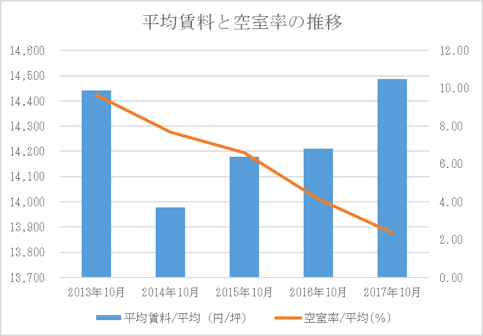
大阪では2014年以降、オフィスビルの新規供給が少なく、2016年には新規オフィス供給がなかった。
直近では、2017年の北区で「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」が供給された。今後の計画は2018年に「新南海会館ビル」(中央区)、2020年に「平野町4丁目オフィスビル」(中央区)、2022年に「大阪神ビルディング・新阪急ビル建替計画」が予定されている程度であり、供給が逼迫した状況は今後も継続する。
更にここ数年来、オフィスビルが建替されてマンションやホテルに替わる等の要因により、中小規模クラスの既存オフィスビルも減少している。
以上から、2018年はオフィス供給減に対し、企業のオフィス需要増から需給アンバランスにより、大阪オフィス市場は空室率の低下、賃料の上昇が続行すると予測した。
住宅地の地価
Point1
2017年と同様、近畿圏の主要中心部では国内外の投資需要により地価・不動産価格は、上昇率は鈍化しつつも未だ上昇を継続している。
収益用不動産の高騰から投資採算ベースに合わないため、収益用不動産の購入に金融機関が融資に慎重になり、2017年後半の取引は購入側も積極的姿勢が後退している。
しかしながら、売手側は強気であるため、価格ミスマッチにより成約件数は減少傾向にある。
Point2
利便性・住環境の良い立地に住宅需要が集中し、地価が上昇する反面、利便性に劣り、高齢化が進んでいる郊外型ニュータウンや旧集落では需要離れが加速化し、地価二極化が鮮明化し、底値感が探れないエリアも多く出てきている。
従って、2018年の住宅地の地価は上昇率を強めるエリアと下落率を強めるエリアの差が大きくなり、地価横ばいエリアは減少していくものと予測した。
Point3
中古住宅の活性化を図るべく、宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月1日から施行される。
改正内容は中古住宅を取引する際には宅地建物取引業者は売主又は買主に建物状況調査(インスペクション)を行う業者を紹介し、希望があれば斡旋するとともに、結果を買主に説明し、売買契約時に現況を相互に確認し、書面で交付することが義務付けられた。
更に、中古住宅の検査と保証がセットになった既存住宅売買瑕疵保険の活用も合わせて、需要の中古住宅への不安が低減されることから、2018年は中古住宅の流通が活発化していくものと予想した。
住宅賃料
近畿圏の賃貸需要は首都圏、中京圏に比すると昨年に引き続き、芳しくない。
国土交通省「平成28年度 住宅市場動向調査」(平成29年3月)によると、世帯主の平均年齢は、首都圏38.8歳、中京圏39.9歳、近畿圏39.4歳と39歳前後に集中しており、差はあまりない。世帯年収は首都圏519万円、中京圏522万円、近畿圏410万円と近畿圏は三大都市圏内で最も低い。この傾向は平成24年度から変わらない。
「支払家賃 + 共益費」でみると、首都圏が86,513円、中京圏70,012円、近畿圏75,653円で中京圏より支払コストは高い。
更に勤務先からの住宅手当があるのは首都圏21.4%、中京圏34.4%、近畿圏22.0%と中京圏は手厚い。世帯主の職業では三大都市圏とも「会社員・団体職員」の占める割合が最も高い。(首都圏47.7%、中京圏53.3%、近畿圏39.7%)
近畿圏の特徴としては、他圏より「自営業」「派遣社員・短期社員」「無職」の割合が高い。
家賃の負担感については、負担感がある(「非常に負担感がある」「少し負担感がある」の合計)割合は、首都圏58.8%、中京圏56.6%、近畿圏は58.1%で首都圏が最も高いが、前述、支払コストが年収に占める割合、即ち、家賃負担率は首都圏20.0%、中京圏16.1%、近畿圏22.1%で、近畿圏が最も高くなっている。
需要の賃貸住宅を選ぶ理由としては、首都圏も近畿圏も「家賃が適切だったから」と家賃重視が最も高い割合を占め、次に「住宅の立地環境が良かったから」「住宅のデザイン・広さ・設備等が良かったから」と続くが、「デザイン・広さ・設備」の重要視割合は、平成26年度以降、低下傾向にあり、賃貸ユーザーの重視ポイントは「家賃」と「立地」に集約されている。
なお、近畿圏は「昔から住んでいる地域だったから」が他圏より大きく、地縁的選好性が高い。
設備等に関する賃貸住宅の選択理由として、首都圏・中京圏は65%前後が「住宅の広さが十分だから」を選んでいるのに対し、近畿圏では35.0%となっている。
各圏とも過半数が重視しているのは「間取り・部屋数が適当だから」である。
「住宅のデザインが気に入ったから」は、中京圏は選択理由の割合が上昇しているのに対し、首都圏・近畿圏は反対に低下している。
こうした需要動向調査をみると、近畿圏は「台所の設備・広さ」「浴室の設備・広さ」「住宅の広さ」への選択理由の割合が低い。弊社調査においても、「大阪市」「北大阪」「阪神間」の需要が多いエリアでは近年、専有面積の小振化か進行しており、家賃負担の限界から「立地」を重視する以上、「広さ」は我慢せざるを得ない。
大阪市の「1K−1LDK」はここ3年〜4年で占有面積は約1坪(3.3㎡)も縮小していることから、今後は縮小傾向に歯止めがかかってくると予測されるが「狭めで安定」なので、住宅事情は改善されない。
反対に「3K−3LDK」は投資目的の購入が増加していることから、分譲マンションの賃貸化が進んでおり、「広めで高額賃貸」と、賃貸住宅市場は二極化が顕著になるものと予測した。
分譲マンション価格
2018年の首都圏における新築マンションの販売戸数は1〜10月間で約26千戸、中古マンションの成約戸数は同期間で約32千戸と中古マンションの成約件数は、新築マンションの販売戸数より約2割上回った。平成2年に「住宅土地統計調査」にて集計開始以降、初めて中古マンションの成約件数が新築マンションの販売戸数を上回ったのが平成28年で、首都圏のマンション供給が新築から中古にバトンタッチした住宅史に残る年であった。
近畿圏では2018年1〜10月間では新築マンションの販売戸数約16千戸に対し、中古マンションの成約件数約14千戸で、新築供給が上回っている。
この首都圏と近畿圏の差は新築マンションの販売価格にあると思われる。首都圏の2018年(1〜10月)の新築マンションの平均価格は5,960万円、同期間の中古マンション成約価格3,185万円と中古マンションの成約価格を新築マンション価格は約87%上回っている。
更に、国税庁調べ「平成28年度 民間給与実態調査結果」の東京国税局内、給与所得者の平均給与は4,886千円であり、新築マンションの平均価格は給与取得者の平均年収の約12倍となっている。
一方、近畿圏の新築マンションの平均価格は3,812万円、中古マンションの成約価格2,072万円で、中古マンションの成約価格を新築マンション価格は約84%上回っている点は、首都圏と大差はないが、新築マンションの平均価格は大阪国税局内平均給与4,180千円の約9倍で、首都圏を下回っている。
なお、独立行政法人住宅金融支援機構による2016年度「フラット35 利用者調査報告」では、マンション購入者の年収倍率は首都圏7.2倍、近畿圏は6.7倍で、近畿圏は全国平均6.8倍を下回っている。
このように、最近の新築マンションの高騰により、需要が中古マンション市場に流れていると言える。
但し、「価格による経済性」だけでなく、国土交通省調べ「住生活総合調査」の平成15年調査と平成25年調査を比較すると、下表のとおり、平成15年調査では「持家世帯」、「借家世帯」も約7割台が取得する住宅は「新築住宅」と回答していたのが、平成25年では「持家世帯」の過半数、借家世帯の約半数が「新築にこだわらない」「中古住宅を選択」し、中古住宅へのこだわりが低下していることも中古マンション市場が活性化している要因の一つであると考える。
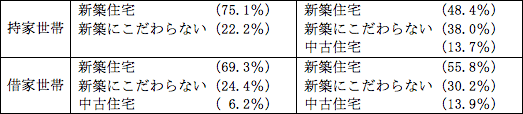
2018年のマンション市場も新築マンションの価格上昇により、需要は中古マンションに流れる傾向は変わらないと予測する。都心立地の新築分譲マンションは投資家(外国人も含める)による購入が過半数を占め、契約率は良いが、供給されるマンションに「住」に対するこだわり・提案がみられず、画一的になっている。
このようなディベロッパーの姿勢もエンドユーザーが中古マンションを選択する一因になっていると思われる。
