コロナウイルス感染症が不動産市場に与えた影響について
コロナ禍での住宅賃貸市場
「Ⅰ、関西住宅賃料の動向」では、総額賃料では2021年に下落している地域が多い。これは、2019年12月に中国武漢市で端を発した新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、日本でも2020年に緊急事態宣言が発令され、人流の制限がされたため、賃貸市場も弱気にふれたためと考えられる。
2022年では、総額賃料が上昇している地域と、下落している地域がみられたが、供給件数が激減していることも要因と考えられる。但し、コロナ禍でリモートワークが普及したため、広目の住宅需要が生じ、「2K-2LDK」の型式の供給が2022年では若干増加している。
2023年は、供給量は全ての型式で増加したが、中国でのコロナ流行並びに2022年2月 ロシアのウクライナ侵攻により、供給制限や円安により、建築資材不足や価格上昇を反映して建築費が高騰した。更に、諸物価、人件費も上昇しており、こうした背景のもと、家賃も上昇している。
コロナ禍での賃貸需要の動向
2020年、2021年は、人流の制限もあって、都心の大学受験者も減少し、地元受験者が増加して、都心部ではシングルタイプの空室がみられた。
また、ステイホームの要請並びにリモートワークの普及もあって、家庭で仕事ができる環境を求めて、広目の住宅の需要が増加して、都心から郊外への移動も見受けられた。
そのため、新規供給は、「1ルーム」「1K」が中心であったが、「1LDK」「2DK」「2LDK」の型式の新規供給が増加し、建築費の高騰により、総額賃料の上昇を抑えるため、近年、占有面積の小振化が進行していた流れもストップし、若干であるが、占有面積は徐々に広めになっている。
関西圏の賃貸需要の世帯年収は、454万円で、首都圏の541万円、中京圏の525万円より低く(「令和3年度 住宅市場動向調査」令和4年3月 国土交通省調べによる)、勤務先からの住宅手当は三圏の中で最も少なく(「住宅手当を受けている。首都圏37.4%、中京圏30.2%、近畿圏21.9%」「住宅手当を受けていない。首都圏57.8%、中京圏69.8%、近畿圏76.1%」)、その住宅手当の平均額も他の2圏に比し、最も低い(首都圏36,665円、中京圏31,009円、近畿圏21,497円)。このため、家賃に負担感がある(「非常に負担感がある」「少し負担感がある」を合算)割合は、近畿圏は50.3%と、半数を超えており(首都圏48.5%、中京圏47.7%)、三圏の中で最も割合が高い。このため、近畿圏の住宅需要は、「住宅のデザイン・広さ・設備」より、「家賃」と「立地環境」をより重視して、賃貸住宅を選択している。また、親・子供との同居・近居の需要も他の2圏に比し、高い特徴を持つ(<表1>参照。)。
<表1>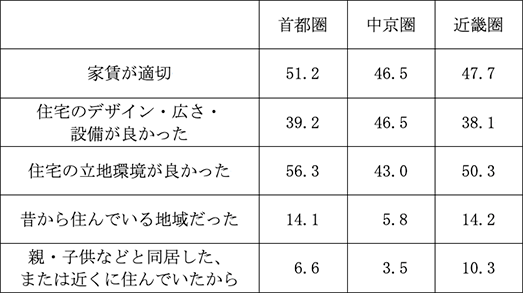
住宅賃料の予測
コロナ禍で従業員を整理していたサービス産業では、観光産業を中心に、人流回復に伴って、需要が回復傾向にあるものの、働手不足の状態にあるところが多い。
物価も上昇しており、賃金も上昇傾向にあるが、中小企業の多い近畿圏では、賃金の上昇は遅々として進まない。
2008年のリーマンショック直前のファンドバブル期には、企業も人員確保のために、家賃補助が手厚かったため、都心に単身者が集中したが、リーマンショック後は、家賃補助をカットしたため、都心のシングルルームは、空室率が上昇した。コロナ禍でも同様の現象が見受けられる。
ファミリー向けでは、広目の中古賃貸住宅、公社・公団住宅は安定した入居率を継持しているが、賃料の上昇した新規賃貸住宅は、完成しても、満室になるまで時間がかかっている状況である。また、コロナ禍で、現在の家賃から低い家賃に住み替えする生活防衛型住み替えも増加しており、賃貸需要からは、賃料・一時金の値下げ圧力があるのに、新規家賃は建築費高騰により、上昇するという、ギャップを生じている。
2023年では、空室率の高い新規賃貸住宅から、家賃の見直しが相次ぐものと思料されるが、賃料上昇に耐え得るのは、大阪市中心6区、北大阪セクター(東・西)、南阪神セクター、東神戸セクターで、そのほかの地域は、賃料の下方修正並びに供給調整が行われるものと予測した。
